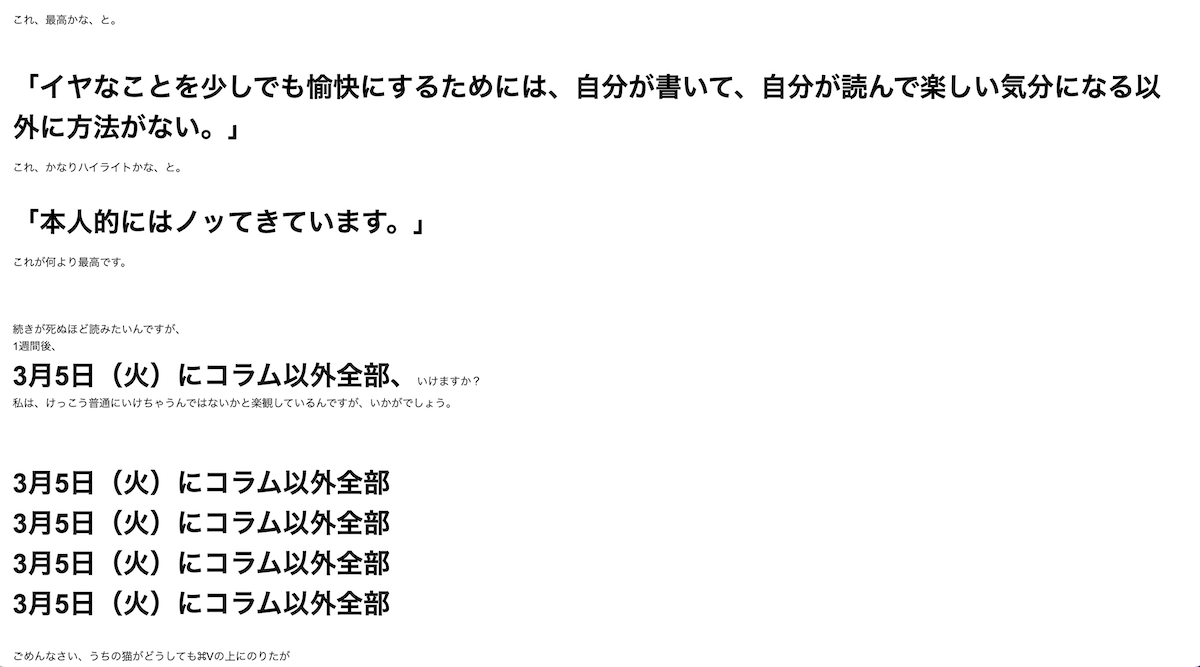ダイヤモンド社
今野良介氏
1984年東京生まれ。ダイヤモンド社書籍編集局所属。早稲田大学第一文学部卒。担当書に『タイム・スリップ芥川賞』『お金のむこうに人がいる』『会って、話すこと。』『読みたいことを、書けばいい。』『会計の地図』『0メートルの旅』『東大卒、農家の右腕になる。』『最新医学で一番正しいアトピーの治し方』『1秒でつかむ』『落とされない小論文』など。『雨は五分後にやんで』に掌編小説を寄稿。担当書籍13作連続重版(和書)。好きな歌手はaiko。
Twitterアカウント@aikonnor。
「自分のアイデアが本当に受け入れられるだろうか?」「もっと良いアイデアはないだろうか?」…など、常に不安と戦いながら創作活動に勤しむクリエイターにとって、作品が形になるまでの間に編集者との間で行われるコミュニケーションは、時に心の支えになるものです。
クリエイターをモチベートする編集者は、日々形のないゴールの見えない創作活動においてどのようなコミュニケーション、特にフィードバックを行っているのでしょうか。プロフェッショナル編集者の「返信」の極意に迫ります。
―著者をはじめ人とのコミュニケーションで普段、意識していることはありますか。
対立関係でも上下関係でもなく、言いたいことを言い合える対等な関係でいたいということです。この仕事のいいところは、共通の目的に向かう協働者として、プロ同士として、年が離れていても誰が相手であっても、対等であれることです。お互いの役割を認め合って、2人で同じ方向を見つめるような関係を築けたらいいなと思っています。
そのために、誰が相手でも適切な距離感でいたいです。適切というのは「自然」というのに近いです。自分から無理に距離を詰めたり空けたりしない。「その人の前に出たときの自分」は、相手によって常に違います。経営者と会うとき、職業の違う人と会うとき、同業者と会うとき、同僚と会うとき、家族と会うとき、それぞれ面と向かったときの適切な距離感は、それまでのお互いが過ごしてきた人生で、もう決まってると思うんです。「距離を詰めなきゃいい関係は築けない」などとどこかで聞いたようなセオリーで考えず、お互いが自分らしくあれる距離を壊さないようにしたいということです。
しかも、立食パーティーで見ず知らずの人と話すのとは違って、仕事相手とは共通の目的があります。「プロ同士、いい仕事をしよう」とお互いが同じ方を向くことができれば、相手との距離感を測り合えるはずです。
―著者やデザイナーへの「返信」で心がけていることはありますか?
原稿やデザイン案を受け取ったとき、いいところがひとつもないということは滅多にありません。少なくとも0が1になったこと、イメージを形にしてくれたことに対する感謝や、うれしさや、労いを自分なりに表現します。その上で、まだまだ原稿がもっと良くなると思うなら、自分の感覚や思考の過程を伝えます。
どこが、なぜいいと思ったか。それでもまだ物足りないことは何か。どこを直してほしいか。それはなぜか。順番に伝えます。直してほしい理由って、大体「もっといける」なんですよ。なので、その前段階の「いけてます」という話から始めないと、直してほしい理由に納得してもらえない気がするんです。
デザイナーへの返信に関しては、「想定している読者と少しズレている」「本の内容より難易度が高く見える」など、編集目線のみのコメントにとどめます。色使いとか、フォントのバランスとか、デザインの専門的なことにはできるだけ口を出しません。知り合いのアートディレクターが、「デザイナーが作ったプロダクトのうち、消費者に理解してもらえるデザイン要素は全体の2割くらいだ」と言っていました。つまりデザイナーは専門家としてこちらの想像を遥かに超えた解像度で考え抜いてデザイン案を出しているので、編集者や消費者として「受け手としてはこう感じた」という目線でコメントするようにしています。
―返信のタイミングは?
早い方がいいと思います。届いた原稿やデザインラフを自分ひとりならばさっとチェックできても、他の人の意見を聞きたかったりもするので、きちんとフィードバックするには多少の時間が掛かります。でも、「ありがとうございます。拝受しました」だけでもいいから最初の返信は早い方がいい。送る側は、「これで大丈夫だろうか……」という不安を抱えながら覚悟を決めて送ってきているはずですから。自分ならどうされたいか、何をされたら嫌か、というのをまず考えます。
―これまでに印象的なエピソードはありますか。
エピソードはなかなかひとつに絞れないですけれど、作る過程が楽しかったという意味で、『読みたいことを、書けばいい。』『会って、話すこと。』の2冊を一緒につくった田中泰延さんとのやりとりでしょうか。1冊目は100万字くらいどうでもいい話をしていました。本の文字数の10倍以上。映画や音楽や次に食べたい料理の話をしたり、「読んでいること自体が楽しかったです」という思いをメール全体で示すのに、面白いと思った部分を太字で強調したり。やりとり自体が面白くなったらいいよな、と。田中さんとは幸運にもそれができたのですが、どの方と接するときも、そうあれたらいいなと思います。
仕事とはまったく関係ない内容を含めたやりとり自体が面白くなったほうが、結果的にアウトプットも面白くなることが多いです。事務的なやりとりばかりしている人に、面白いことを書いて見せてあげようとは思いにくいでしょうし。もちろん、冗談のない緊張関係を続けたほうが良いケースもありますし、相手との関係性次第ですけれども。
―仕事を始めた頃から、「やりとり自体を面白く」というスタンスでしたか。
いやいや、全然(笑)。キャリアの最初は、経理や人事など企業のバックオフィスの人が読む『企業実務』という雑誌の記者でした。原稿は社労士や弁護士、税理士などに書いてもらうのですが、右も左もわからない学生上がりの人間がいきなりプロに記事を書いてもらうわけです。付け焼き刃で勉強するのが精一杯で、やりとりを面白くしようと考える余裕はなかったです。
開き直れたのは、読者が弁護士などのプロではなく、企業の実務担当者だと気づけたことです。つまりわたしは著者よりも読者に近いわけだから、むしろよく知らない自分の知識レベルで理解できる記事を作ればいい。逆に、それ以上はできない。自分自身が読者になればいいんだ、素人目線であり続けることが自分の役割なんだと思ったとき、覚悟が決まりました。
相手が迷うポイントがないように。―ひらりささんの返信術