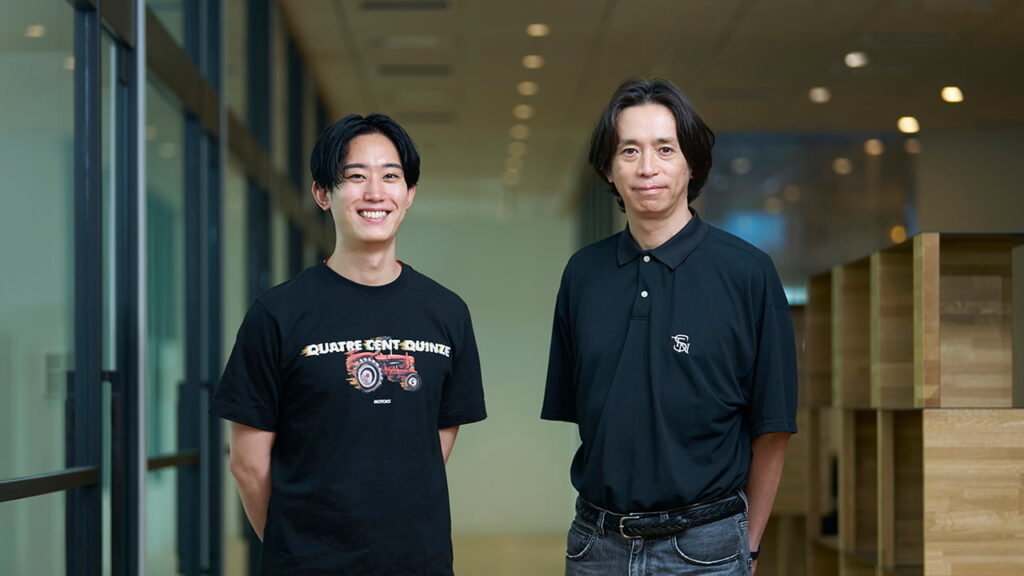会社として初動でできることは少ない。冷静になることが重要
従業員が突然事件に巻き込まれたり、関与し、逮捕されることがある。企業は多くの従業員を抱えており、子会社、関連会社を含めると、その人数は膨大なものとなる。「当社ではそのようなことは絶対ない」と信じたい気持ちはわかるが、そういう事態が発生しないとは言い切れない。
現実に今年に入り、筆者のクライアントでも4社、そうした事態が発生し、初動対応について問い合わせを受けた。
従業員が逮捕されると、通常、結婚していたり、親族と同居していれば、まず最初に家族に連絡がいき、その後、家族から会社に報告があることが一般的だ。まれに、独身者で家族にも連絡をしたくないと通報を拒む被疑者は、当番弁護士を通じて会社に報告される事例もある。そこで社内はパニック状態になり、どうしていいものか、と悩む企業が後を絶たない。
ここで簡単に刑事事件の流れについて説明する。
被疑者が警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に送致しなければならない。任意の事情聴取と違い逮捕状が出ているため、会社の人間が会いたいと言っても被疑者と会うことはできない。この48時間で警察は被疑者を釈放するか送致の手続きを取るかを決めなければならない。
警察が検察官に送致すると、検察官は裁判官に24時間以内に勾留請求するかどうかを決定する。勾留請求しなければ被疑者は釈放される。この場合の釈放は無罪ではなく、多くの場合、被疑者が犯罪を認め、自白し、証拠もあり、証拠隠滅や逃亡もなく、身元も判明している状況のもと、勾留の必要なしとされて釈放されることが一般的である。従って、その後も起訴するかどうかの捜査が継続されるという状態が存在する。逆に否認している場合には釈放されることは少ない。
被疑者の立場から見ると、逮捕からここまでに要する時間は3日間であり、この段階で釈放されていれば、「逮捕」の事実が外部に漏れることも少ないが、往々にして否認事例が多く、その後の勾留によって身柄拘束されてしまうことになる。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は勾留するかどうかを判断し、勾留をしないと判断すれば釈放される。勾留は警察署の留置場か拘置所となる。勾留されると、検察官は10日以内に起訴するかを決定する。この期間で判断できない場合は、勾留期間をさらに10日間、裁判官に延長請求できる。合計20日間となるが、その期間以内に起訴できなければ被疑者は釈放される。
起訴、不起訴のほかに起訴猶予処分があり、例えば、被害者に謝罪、示談、あるいは被疑者の十分な反省などがあり、犯罪の証拠もあるが、起訴は猶予するという意味の不起訴であり、いわゆる証拠不十分の不起訴とは全く違う。
起訴されると、「被疑者」という立場から「被告人」という立場に変わり、身柄はそのまま勾留される。ここで身柄を解放するには保釈請求して身柄を解放してもらうことになるが、統計データから見ても保釈率は20%を割り込んでいる。