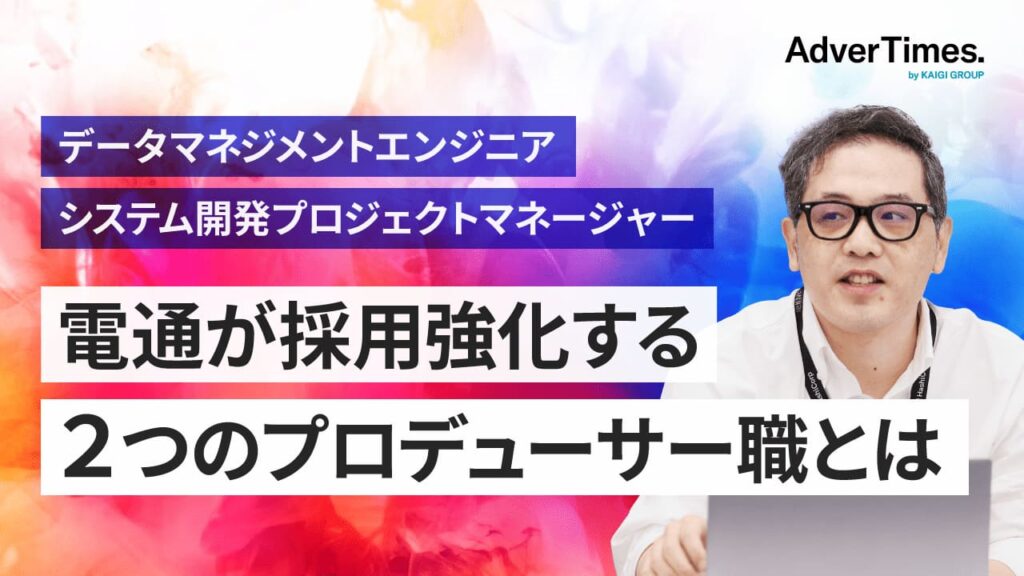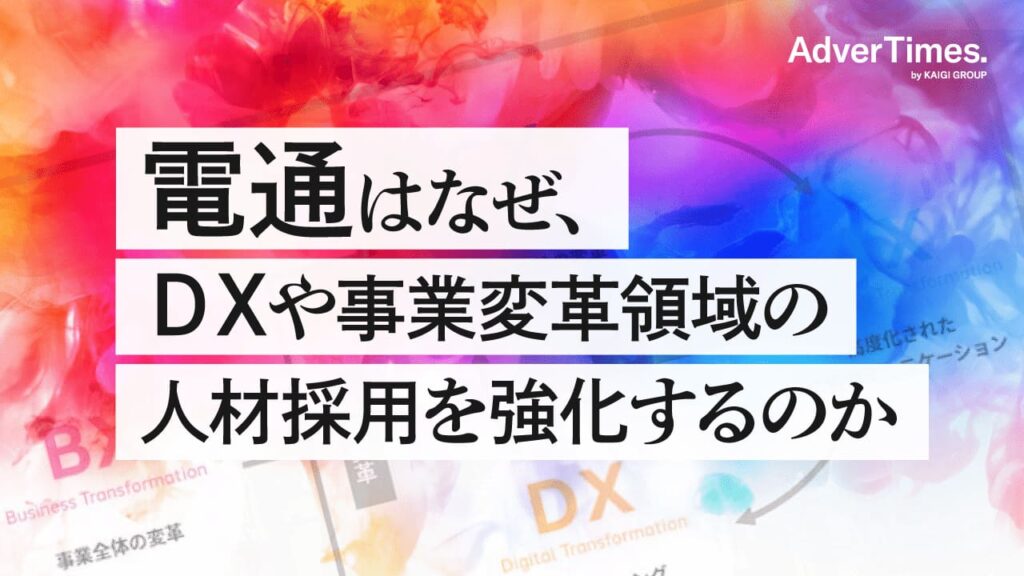近年、AIの登場により、広告コピーが新たな局面を迎えようとしています。広告会社では「コピーライター」という名刺を持つ人が減った、という声も聞きます。しかし、どんなに時代が変わろうと、コミュニケーションや表現の手法が変わろうと、広告コピーの基本は変わりません。だからこそ若い世代の皆さんに知っておいてほしいコピーがたくさんあります。
そこで本企画では、過去から現在にいたるまで、時代と共にあり、これからも「未来につないでいきたいコピー」について、制作者であるコピーライターの皆さんにお話を聞いていきます。
今回は、丸井「好きだから、あげる。」、TOTO「おしりだって、洗ってほしい。」、シャープ「目のつけどころが、シャープでしょ。」など、数々のコピーで知られる仲畑貴志さんにインタビュー。コピーの世界に新しい価値観を生み出してきた仲畑さんに、それぞれのコピーが生まれた背景や企画について、かつて新人の頃に仲畑広告制作所で修行をしたコピーライターの門田陽さんが聞きました。
「野生」の角川、「知性」の新潮
門田:まず、1979年の新潮文庫のコピー「知性の差が顔に出るらしいよ…困ったね。」からお願いします。広告には、桃井かおりさんが登場しました。
知性の差が顔に出るらしいよ…困ったね。
(新潮社/新潮文庫/1979年)
仲畑:これは、ライバルとして角川書店を置き、戦略的にこさえたコピーです。当時、角川は自社で出した書籍を映画化し、莫大な予算を組んで総合的に本を売り出していました。でも新潮文庫のバジェットは、角川とは規模が全然違う。だから、世の中に膾炙している敵の力を利用して話題をつくろうと考えたんです。
あの頃、角川が打ち出していたキーワードは「野生」。小説と映画のタイトルにもなっていました。「野生」の角川に対して「知性」という言葉をぶつけた。対立する図式としてメディアが書きやすくなるように。メディアで喧伝されれば、広告効果がプラスされるわけだから、あえて対立するポジションを取ったわけです。そもそも僕は「知性」という言葉があまり好きじゃないんだけど、本という知識や人間のふくらみに関わる商品には、どのようなコピーがよいか考えた結果、自分に戦略的な縛りを設けて書いたものです。
門田:映画「野生の証明」(1978年 角川春樹事務所)が公開された頃ですね。オリエンのときに新潮社から、「ライバルに勝ちたい」という話があったんでしょうか。
仲畑:ないですよ。自分が勝手に、そのことを意識しただけで、「野生」との対立図式なんてことは当時のプレゼンでも言っていません。このキャンペーンは特定の1冊の本を売るわけではなく、森羅万象の本が揃う「新潮文庫」そのものだったし、「これを言わなくてはいけない」ということも無かったから、人の想いにかかわることはすべてコピーになると考えていました。これはすべのコピーに言えることだけれど、受け手の共感や実感がそのコピーにあればいいんです。
門田:このコピーにそんな背景があったとは、これまで知りませんでした。ちなみに、コピーを言い切りにせず、最後に「…困ったね。」とつけたのは?
仲畑:コピーが企業からの「押しつけ」になるよりも、受け手に「参加する余地」を持たせた方が受け手のココロに届く効果があると考えていたからです。前半の「知性の差が~」に対して、「…困ったね。」という一言で「そう思わない?」という感じが伝われば……。自分の中では「〇〇は、〇〇だ。」という言い切りの古いコピーは、書かないと決めていました。もちろん、ケースバイケースですけどね。
言葉の意味機能からすれば「知性の差が、顔に出る。」だけでよいのではないかと、当時クライアントから指摘を受けました。確かに、言葉の持ちやすさ、使いやすさや伝わるスピードなどを考えると、コピーは短いほうがいい。でも、その言葉に込めた意図は、そぎ落とした機能だけで伝わるわけではないんです。
それを、僕は「エビフライの尻尾」理論と名付けました。エビフライの尻尾は、食べない人がほとんど。でも食べないからと言って、最初から尻尾が取られたエビフライが出てきたら?どんなにおいしかったとしても、それはもうエビフライとしてのビジュアルアイデンティティを持たないものになっていますよね。
このコピーで言えば「知性の差が顔に出る」はエビフライの身、「困ったね。」が尻尾。コピーも意味として伝わる部分だけでは伝わりにくい。まさに「エビフライの尻尾」こそが、多くを伝えてくれるんです。
門田:これはテレビCMもオンエアしていましたが、グラフィックの展開だけだとしても「…困ったね。」はつけましたか?
仲畑:つけています。この頃はまだ、CMとグラフィックのコピーを変えることはなかったですね。キャンペーンのコピーはワンワードの時代でした。
門田:このコピーは、どちらかといえばセリフのようですね。
仲畑:そう、確かにセリフっぽいかもしれないですね。金鳥や関西電気保安協会などのCMをつくっていた電通大阪支社の堀井博次さんたちは、自分たちは「セリフライター」であるという認識で仕事をしていました。それはテレビ主導の広告をつくっていたからかもしれないけれど、テレビだとその方が伝わりやすいのかもしれない。僕は元々グラフィック育ちだけど、あちらのやり方を見ていると、語尾の調子をもっと利用してもいいと思いますね。