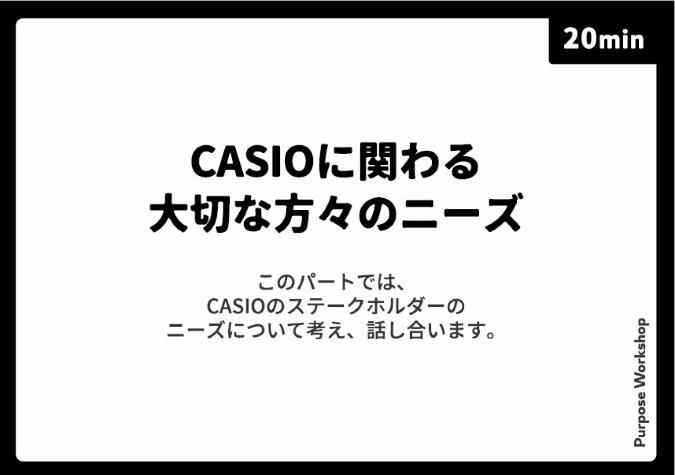※本稿は広報会議2025年4月号を転載しています
創業者が小型純電気式計算機を発明して以降、CASIOでは時計、電子楽器、電子辞書など、斬新な働きを持った製品を生み出すことで、人々の生活を助け、社会を進歩させてきた。こうした考え方は同社の「創造 貢献」という経営理念に表れている。
だが時代が変化するにつれ「創造 貢献」だけでは「何をつくったらいいか」が見えにくくもなっていた。「商品・サービスをつくったその先でどのような社会にしていきたいのか?」未来志向で自社の存在意義を問い直すため、2023年8月よりパーパスとバリューズを策定するプロジェクトを開始。2024年6月に社内発表し共通理解を深めた上で、同年11月に社外発表している。
策定した「パーパス」と「バリューズ」をポスターとして社内に掲出。「このパーパスから、ひとりひとりが変わっていこう。」「今日を超える歓びがあふれる毎日を、社会を、生みだし続けよう。」と呼びかけるメッセージも加え、「自分たちの延長線上に、パーパスがある」と感じられるようにした。
パーパスプロジェクトには、営業、マーケティング、開発、経営企画、人事、コミュニケーション(宣伝・広報)など、ほぼ全部門のメンバーが参画した。その中核を担ったのは、各部門の架け橋となり、社内発信にも長けているコミュニケーションデザイン部。パーパス策定にあたっては、ワークショップなどを通じて国内外の2000人以上の社員の声を集約した。
プロジェクトを率いた同部の小野洋子氏は、次のように話す。
「CASIOには長い歴史を紡いできた事実があります。CASIOの存在意義は、社員を含むステークホルダーの中に必ずあります。それを“発見する”のがパーパス策定のプロジェクトだという認識を持っていました。これまでの実績や現場のリアリティを無視したパーパスではわざとらしく不自然で、誰の賛同も得られません。立場の異なる様々な視点の意見を集めてパーパスの源泉にしていきました」。
同社はパーパスブランディングを支援するSMOと組み、パーパス策定のプロジェクトを次のようなステップで進めていった。
まず2024年1月~2月頃、有志の社員を募り、2種類の「ワーク」を行っている。1つが自主ワークで、「意見抽出ワークキット」を用い、「企業の強み」「ステークホルダーのニーズ」などを記入できるようにした。もう1つが対面で行うリアルの「ワークショップ」。これは全3回実施している。これらのワークを通じて、「驚きのあるものを届けたい」「親しみやすい存在でありたい」といった社員が抱いている思いや、「独自性がある」「ユニーク」「品質にこだわっている」などの同社の強みを集めていった。
こうした策定のプロセスが、一部の社員だけに閉じられたものだという印象を持たれないよう、社内ポータルサイトでは定期的に記事を発信し、経営層には会議で進捗報告を実施するなどして、情報開示を行ってきた。
また、このワークと同時並行で、役員や社外のステークホルダーへのヒアリングを実施。こうして集めたデータをもとに、プロジェクトメンバーが、内容を集約。同年4月頃、候補案を4つに絞り社員に提示、社員投票を行った。そして経営陣による吟味を経て、6月に社内発表している。
「たくさんの方にお話をうかがいましたが、印象に残ったのは、課題に思う点や、強みと捉えている点は結構一致していて、同じ方向を向いていたことです。表面上はバラバラに見える場面があったとしても、CASIOの社員の芯の熱さは同じ。一致団結したら強いぞ、と気持ちが高まったのを覚えています。社内からは想定以上の反響がありました。候補案の投票時も自由記述欄にたくさんの書き込みが見られ励まされましたね。企業の成長において最も避けたいのは『無関心』ですので、社員が積極的に関与してくれたことは大きな意味があります。社内でパーパスを発表した時、一番多かったフィードバックは『決まってよかった』『策定お疲れ様』といった、ねぎらいの声でした。社員みんなでつくったパーパスだと感じています」(小野氏)。
プロジェクトにはグローバルのグループ会社社員も関わった。国内と同様に、自主ワークでの意見抽出や、選出メンバーによるリアルワークショップへの参加、最終段階の候補案へのアンケートに参画している。こうした巻き込みが実現できたのも、海外担当の役員、各グループ会社の社長らの協力があってこそだと小野氏は振り返る。
「策定フェーズにおいては、本社のある日本と、各国社員との温度差が生じてしまうことに課題を感じていましたが、浸透フェーズにおいては、社員一人ひとりが自らの業務にどう結び付けられるかを考え、実践できる環境づくりに注力していきます」。
国内外からできる限り幅広く意見を集め、想いに耳を傾けることを目的に、パーパス策定の過程で、社員が自主ワークに参加できるようにした。ステークホルダーのニーズなど、自身の考えを記入できる「意見抽出ワークキット」を展開し、社員が未来志向を持つ機会をつくり出した。
パーパスは、同社の意思決定や行動の指針であると同時に、「どんな社会にしていきたいか」を未来志向で考えるための“道しるべ”だ、と小野氏は話す。今回、パーパスとともにバリューズも策定したことで、日々の業務でパーパスを実践するための価値観・信条も明確になったという。
パーパスを基点とした意思決定が行えることを目指し、役員や部門長を対象にしたパーパスの本質理解を深めるワークショップも実施。パーパスにつながる顕著な行動を評価するアワードの設置も検討していきたい考えだ。
ワークショップの様子。異なる部門の社員同士が対話することで、新たな視点が生まれた。