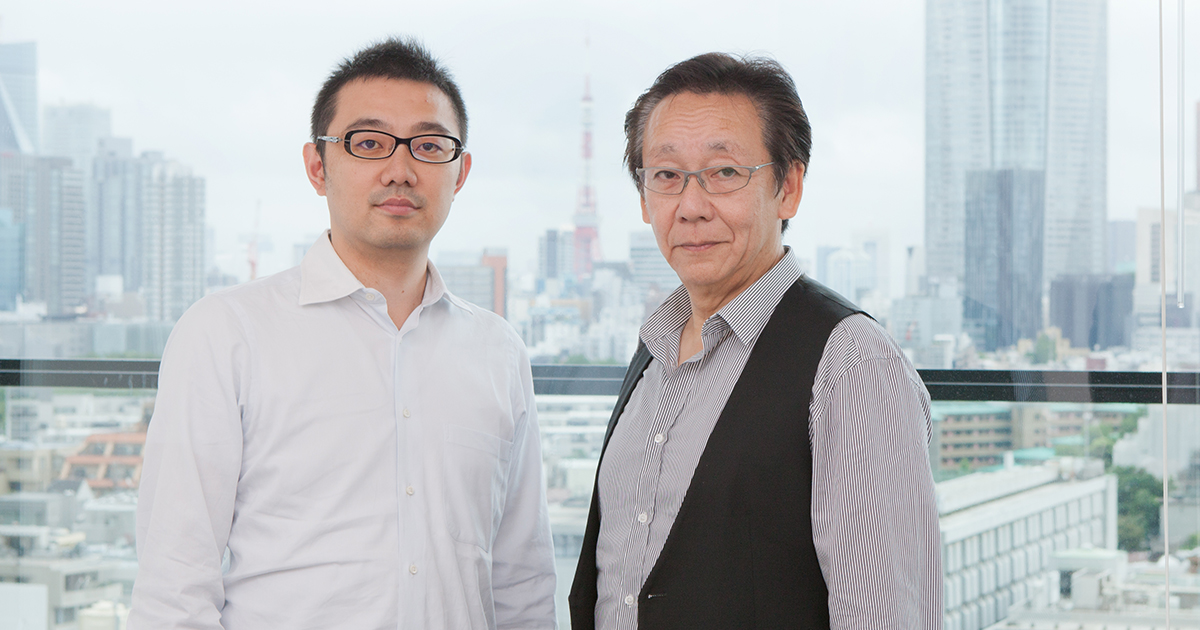吉良:今の世の中における「マンガ」というコンテンツについて、佐渡島さんのお考えを聞きたいと思っています。僕がすごく興味があるのは、マンガの仕組みはなぜこんなに長い間変わらないのか?ということ。1959年に創刊された少年マガジンや少年サンデーの頃から、出版物の形式や編集者の仕事がデジタルの時代になっても、ずっと変わらないようにみえるのはどうしてなのでしょうか。
佐渡島:僕は逆に、大きく変わってきていると思っています。マンガの歴史の一番初めは貸本から始まっていて、次が雑誌の時代です。過去の歴史を見ていて面白いなと思ったのが、雑誌の時代には単行本を出すことが恥ずかしいと思うような風潮があったんですよ。作家の収入が雑誌の原稿料で占められていた時には、「単行本にしないと分からないようなマンガを描いているなんて、かっこ悪い」という価値観がありました。それが途中から、単行本で収益を得ていくという考え方に変わっていきます。
だからこの50年、60年の間に出版社も3回くらいモデルチェンジをしているんです。出版ビジネスにおける「お金を得るポイント」が、10年や15年をかけて緩やかに変わっていくということを経験しているんですね。これまでは「紙の本」という領域で変化していたから、流れが緩やかで対応できていたけれど、今はそれが「デジタル」という領域での急激な変化なので、対応しづらくなってきているのだと考えています。
「気づけなさ」に気づかない限り、デジタルの世界は理解できない
吉良:その原因はやはり、メディアが世界に拡がってきていることが大きいのでしょうか?つまり、今まで日本の媒体は、日本国内でしか読まれていませんでした。ところが、Web上にコンテンツを載せると、世界中の人がアクセスすることができてしまう。そこへの対応も必要だと思いますが。
佐渡島:なるほど。海外から見ることができるとはいえやはり言語の壁があって、自動翻訳にもまだ限界があるので、そこの差はまだ大きいと思っています。ただ、リアルな物が動く時代では、新しい取り組みを全員がそれを目にするので理解ができたんですよ。「貸本が雑誌に変わったな、雑誌が単行本になったな」と。最近はみんな単行本を読んでいるな、と気づけたものが、インターネットの中ではいくら流行っていても、物がないから存在に気づけない人がいる。
だからデジタル側で大きい変化が起きていても、意図的にデジタルに触れていないと、まったく気づかないということが起こる。デジタルはその中に入ってしまえば、大きな変化や商品が売れていることを実感できますが、その外にいると完全に「無」なんです。その「気づけなさ」っていうのに対して、能動的に気づかない限りデジタルの世界は理解できないっていうことですよね。急激なビジネスの変化に対応できる人とできない人の差が生まれているんだなと感じています。